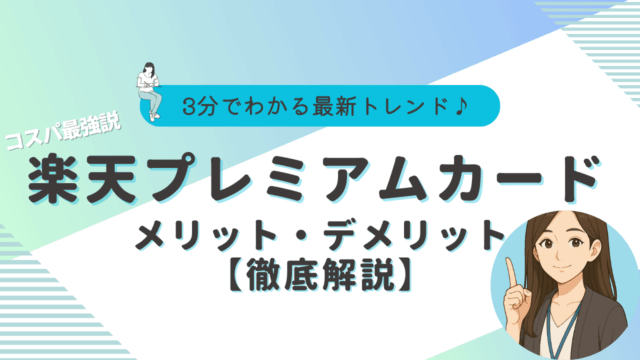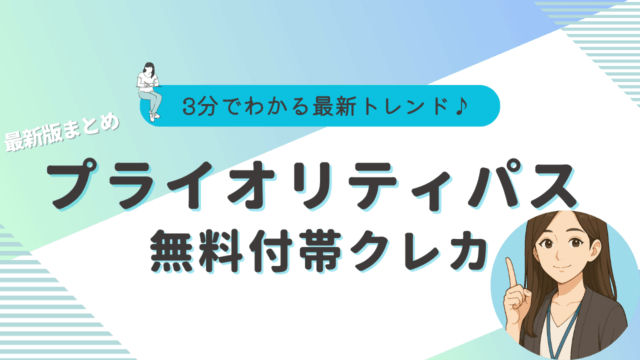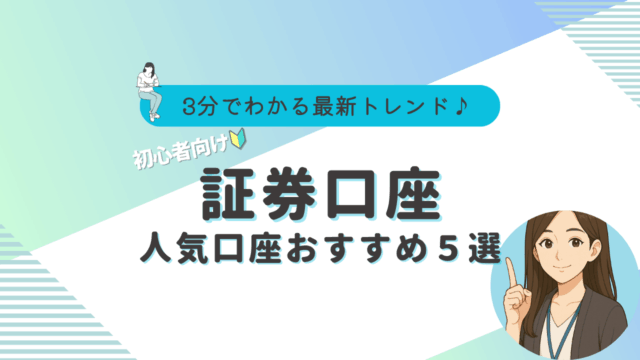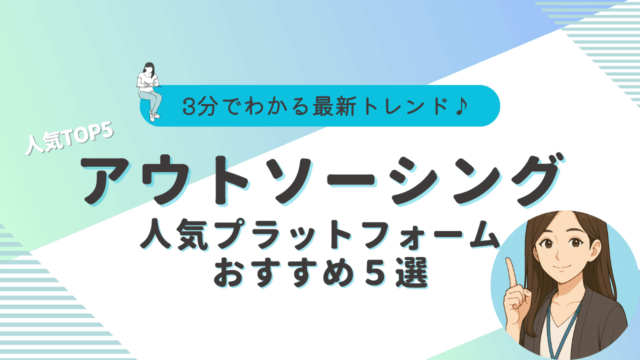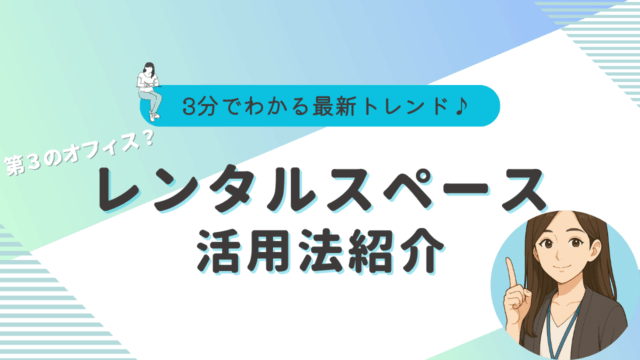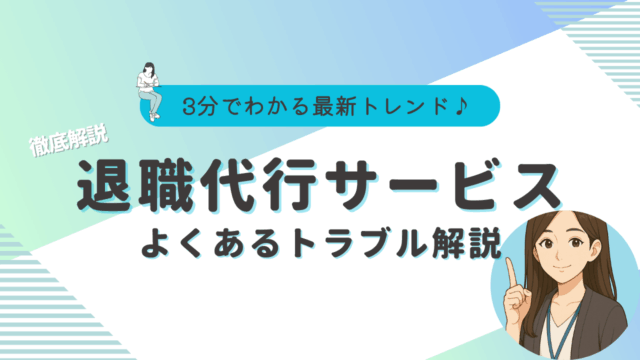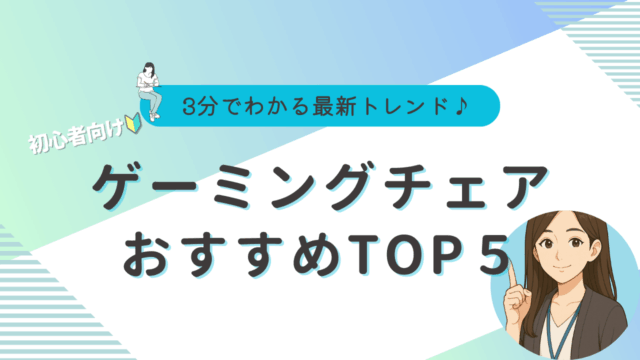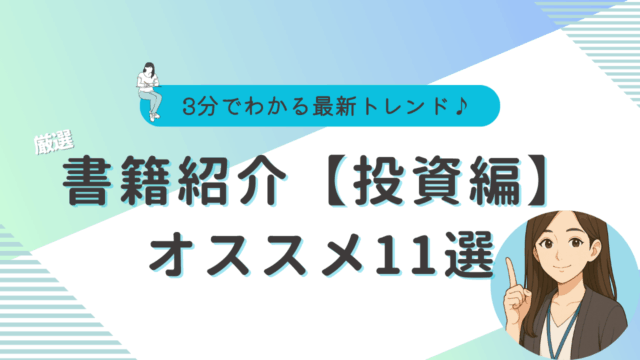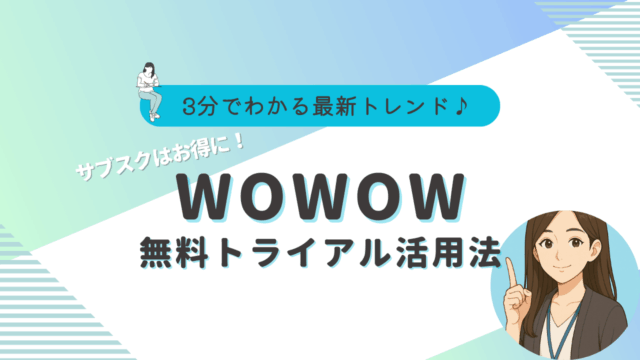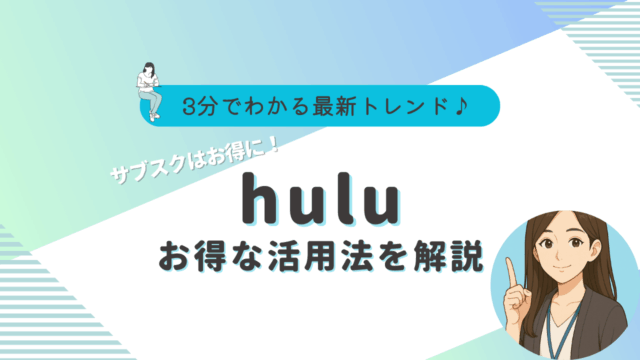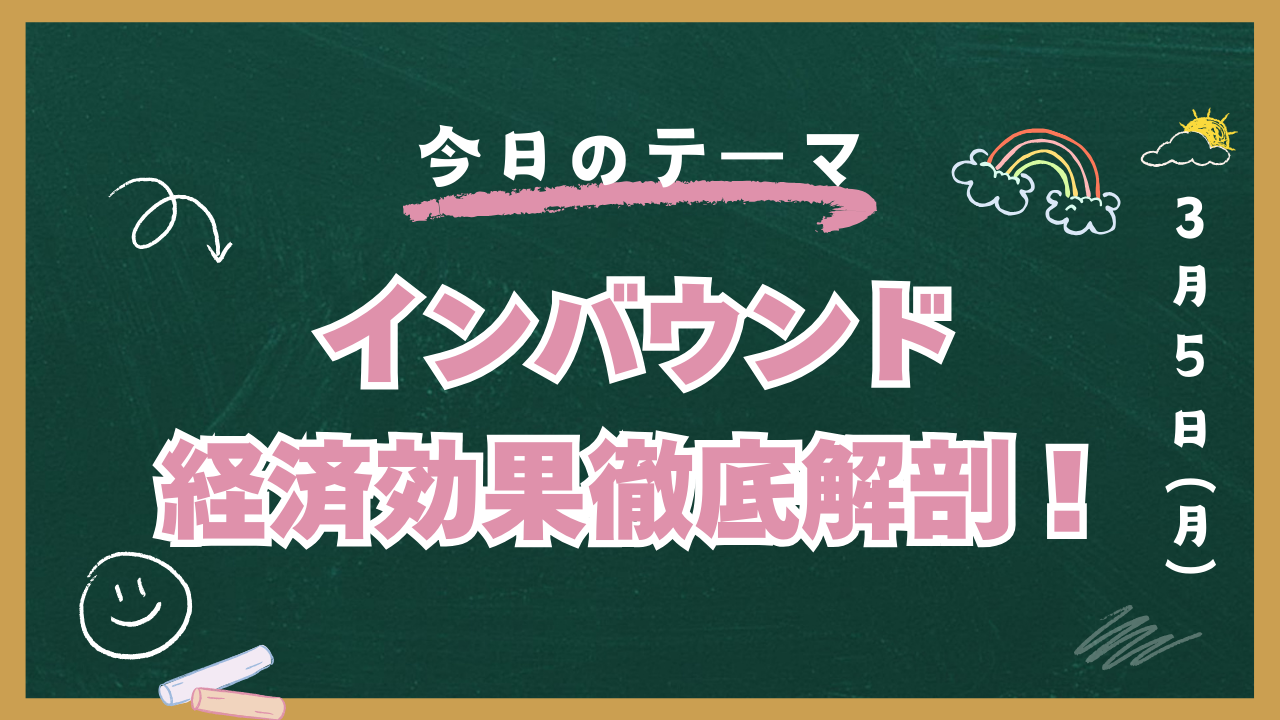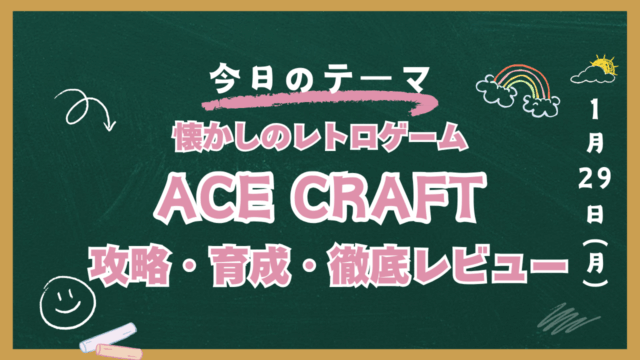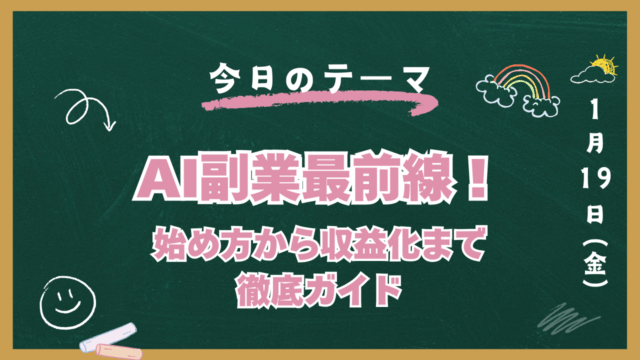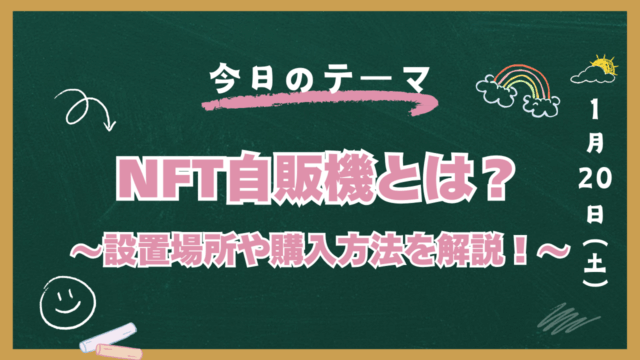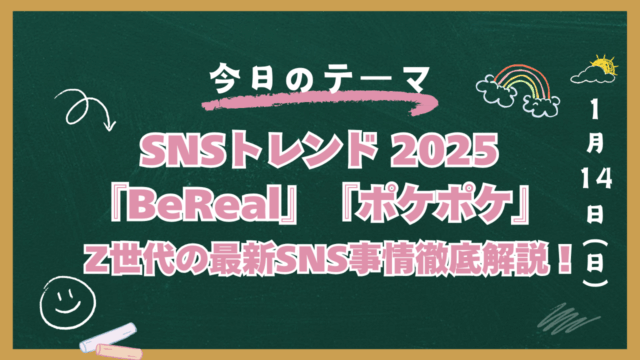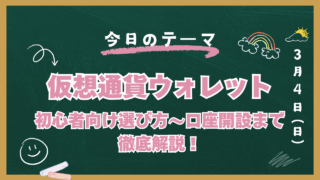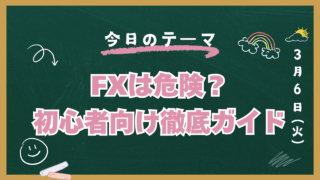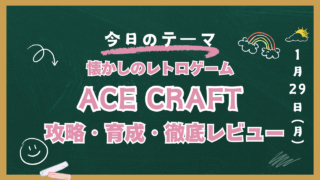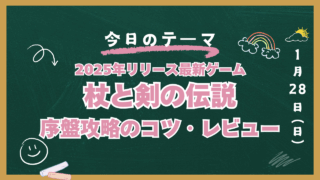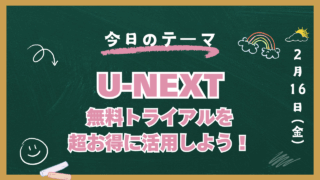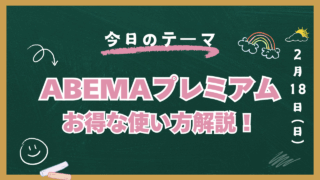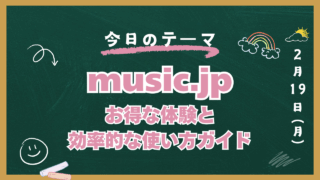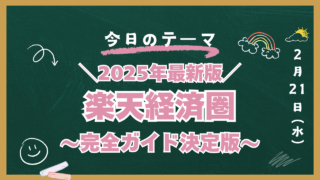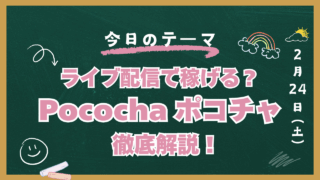もくじ
- インバウンド 経済効果は「量×質×分散」
- データで俯瞰するインバウンド 経済効果
- 仕組みで理解するインバウンド 経済効果(直接→間接→誘発)
- どこに伸びしろがあるか:インバウンド 経済効果の「質」を高める5ポイント
- 【比較】地域タイプ別にみるインバウンド 経済効果の伸ばし方
- 施策×費目の対応で「数字」を動かす
- 体験談:長野の小旅館が「単価×稼働」を同時に伸ばした話
- 現場でインバウンド 経済効果を高める10ステップ
- 外部環境と先行指標:円安・イベント・政策が与えるインバウンド 経済効果
- FAQ:インバウンド 経済効果のよくある疑問
- まとめ:インバウンド 経済効果は「分かる→整える→分散する」でまだまだ伸びていく見込み
インバウンド 経済効果は「量×質×分散」
インバウンド 経済効果は、①来訪者数の増勢(量)、②旅行消費単価と滞在日数の引き上げ(質)、③都市集中から地方・オフピークへのシフト(分散)の三拍子で、今後さらに大きく伸びます。つまり、日本の受け入れ側が多言語対応・キャッシュレス・事前決済・周遊導線を設計できれば、結果として地域に残る付加価値が増えます。
例えば、2024年の訪日外国人旅行消費額は8.1兆円(過去最高)で、2025年7月の訪日外客数は343.7万人(7月として過去最高)という追い風が続いています。(MLITJapan National Tourism Organization参照。)
一方で、為替への過度依存・人手不足・オーバーツーリズムは課題です。そのため、需要の平準化(分散)と現場DXを同時に進める視点が欠かせません。なお、旅行・観光の日本GDPへの寄与は2024年にGDP比7.5%規模との見通しで、したがってマクロの柱として再確立しつつあります。
データで俯瞰するインバウンド 経済効果

まず、全体像を一次情報で押さえます。さらに、量(人数)と質(消費)の両面を同時に把握すると、政策や現場の優先順位が見えます。
最新KPIスナップショット(2024→2025)
| 指標 | 2019(参考) | 2024 | 2025年の足元 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 訪日外客数 | 31,900,000 | 36,870,000 | 2025年7月 3,437,000(月間7月最高) | JNTO/報道 ReutersJapan National Tourism Organization |
| 旅行消費額 | 約4.8兆円 | 8.1257兆円(確報) | - | 観光庁(確報) MLIT |
| 費目構成 | - | 宿泊33.6%/買物29.5%/飲食21.5% | 2025年1–3月:宿泊33.5%/買物29.4%/飲食22.3% | 観光庁(確報/速報) MLIT+1 |
| マクロ寄与 | - | GDP比7.5%見通し | - | WTTC World Travel & Tourism Council |
つまり、人数×消費の両輪が過去最高圏にあり、「受け入れの設計次第」でインバウンド 経済効果はさらなる底上げが期待されます。
仕組みで理解するインバウンド 経済効果(直接→間接→誘発)
まず、旅行者の支出は直接効果(第一次効果)として宿泊・飲食・小売・交通に現れます。さらに、仕入・物流・清掃・IT・広告などの間接効果(第二次効果)に波及します。つまり、地域のサプライチェーン全体が動きます。
加えて、雇用・所得の増加や設備投資を通じて誘発効果が続くため、結果として地域経済の循環が強まります。
波及の見取り図
| 層 | 主な主体 | 例 | 期待される成果 |
|---|---|---|---|
| 直接(第一次) | 宿泊・飲食・小売・交通 | 客室・食・土産・運賃 | 売上・粗利・直接雇用 |
| 間接(第二次) | 仕入・清掃・IT・広告 | リネン、食材、予約SaaS | 取引先売上・物流活性 |
| 誘発 | 家計・投資 | 消費拡大・設備更新 | 地域所得・投資循環 |
どこに伸びしろがあるか:インバウンド 経済効果の「質」を高める5ポイント
-
客単価(ARPU):高付加価値の文化体験・自然体験・ウェルネスを組み込み、さらに**動的料金(ダイナミックプライシング)**で繁閑差を最適化。
-
滞在日数:都市+地方をつなぐ周遊導線を整備し、つまり「もう一泊」の理由を明確化。
-
季節分散:一方で、混雑時は体験の希少性が下がるため、オフピーク商品の設計で満足度×客単価を両立。
-
地域分散:そのため、二次交通×デジタルチケットで移動摩擦を下げ、ナイトタイムエコノミーで時間分散も。
-
購買摩擦の低減:例えば、キャッシュレス×免税ワンストップで会計時間を短縮。さらに、店頭のカード導線は決済×ポイント還元設計と親和性が高い(クレジットカードの基礎知識)。
【比較】地域タイプ別にみるインバウンド 経済効果の伸ばし方
地域タイプ別の強み・痛点・打ち手
| 地域タイプ | 強み | 痛点 | 打ち手(例) |
|---|---|---|---|
| 大都市(東京/大阪/京都) | 需要・アクセス | 混雑・単価頭打ち | 分散観光パス、夜間ミュージアム、事前決済 |
| 定番観光地(箱根/日光/沖縄) | 認知度 | 季節偏り | オフピーク割、雨天代替コンテンツ |
| 地方自然(東北/信州/四国山間) | 自然/静けさ | 二次交通 | 英語案内×デジチケ、体験予約DX |
| スノー/アウトドア | 冬需要 | 人手不足 | シェア人材・短期多言語サポート |
例えば、短期の多言語サポートは外注×シェア人材が現実的です。つまり、制作・翻訳・SNS運用はクラウドソーシングでの案件が今後も増加することが予想されます。(クラウドソーシングの始め方)。
施策×費目の対応で「数字」を動かす
観光庁の確報では費目構成:宿泊33.6%/買物29.5%/飲食21.5%が中核です。したがって、摩擦を下げる施策がインバウンド 経済効果の本丸を直撃します。
費目×施策の対応表
| 主費目 | 伸ばし方 | 具体 | 根拠/背景 |
|---|---|---|---|
| 宿泊 | 価格設計 | 週末の動的料金、連泊割 | 宿泊比率が最大で影響大 |
| 買物 | 会計摩擦↓ | 免税一体化、キャッシュレス | 買物29.5%で効果大 |
| 飲食 | 情報摩擦↓ | 多言語メニュー/アレルゲン表示 | 飲食21.5%の取りこぼし防止 |
| 交通 | 周遊設計 | 二次交通×デジチケ | 地方分散・滞在日数↑ |
キャッシュレスや送金、ポイント還元などの設計はフィンテックの理解が効きます。
体験談:長野の小旅館が「単価×稼働」を同時に伸ばした話
まず、客室12室の温泉旅館Aは、欧米豪の個人旅行が増えた一方で英語案内と会計の詰まりが課題でした。
-
毎週10分×英語ロールプレイでチェックイン/食事/温泉マナーの定型化(具体的な学び方は 英語学習の始め方 を参照)。
-
ダイナミックプライシングと連泊割で価格を最適化。
-
免税×キャッシュレスの一体導線を導入し、さらに事前決済で到着時の待ち時間を5分短縮。
-
UGC(宿タグ)と短尺動画で発信。
結果として、平均客単価+18%・平日稼働+8ptを達成。さらに、客室ではエンタメ体験として内部 U-NEXT や ABEMAプレミアム を案内し、滞在満足度を底上げしました。
現場でインバウンド 経済効果を高める10ステップ
-
KPIを一言で定義(来訪者数・ARPU・滞在日数・再訪率)。
-
混雑ヒートマップを見える化(曜日/時間/季節)。
-
多言語の“必須”だけ先に(料金・アレルゲン・緊急時)。
-
キャッシュレス+免税の一本化(POS/レジ/書類)。→ クレジットカードの基礎知識
-
体験を事前予約×事前決済(在庫平準化・ノーショー減)。
-
オフピーク商品を設計(雨の日パス、平日限定、早朝/夜間)。
-
UGC施策(レビュー導線とハッシュタグの“言い方”を店頭掲示)。
-
英語ルーティンを週1回(10分×3セット)。ノウハウは内部 英語学習の始め方
-
CSVで月次振り返り(売上・客層・原価・時間帯)。ワークフローは内部 Notion でテンプレ化。
-
来期の繁忙期を“いま”仕込む(OTA・KOL・ツアー会社)。
最新統計はJNTO(訪日外客統計)・観光庁(インバウンド消費動向)、マクロはWTTCで定点確認が安全です。
外部環境と先行指標:円安・イベント・政策が与えるインバウンド 経済効果
まず、円安は外貨ベースの割安感を通じて来訪者数と消費を押し上げました。さらに、2024年の年間外客数が過去最高・消費8.1兆円という記録はその象徴です。つまり、為替要因に頼り切らず、体験価値の磨き上げに振るのが次段階です。
加えて、**大型イベント(例:大阪・関西万博等)**は追加の誘客トリガーになりえます。Reuters
FAQ:インバウンド 経済効果のよくある疑問

Q1. インバウンド 経済効果はいつまで続く?
まず、人数と消費は回復・更新トレンドです。さらに、体験価値・地方分散・人材育成が回れば持続可能性は高まります。一方で、為替・地政学・災害のリスクがあるため、したがって複線の集客(多市場)と運用DXが安全策です(統計は JNTO/観光庁/WTTC を参照)。
Q2. 個店レベルで今すぐできる三つは?
多言語案内・キャッシュレス・予約前決済です。さらに、平日割の体験付で滞在日数と客単価を伸ばしてください。加えて、社内の英語は短時間×高頻度が近道(英語学習の始め方)。
Q3. どこで最新の数字を確認すべき?
そのため、訪日外客数は JNTO、消費は 観光庁(インバウンド消費動向調査)、マクロ寄与は WTTCが一次情報として有用です。
Q4. IT投資の優先度は?
例えば、キャッシュレスと免税一体化→体験の事前決済→多言語メニューの順が費用対効果が高いです。さらに、会計や還元の導線は内部 クレジットカードの基礎知識 と親和性が高いです。
Q5. 宿泊の付加価値づくりのコツは?
一方で、客室エンタメやローカル体験の同梱が有効です。つまり、U-NEXT・ABEMAプレミアム のような内製ガイドを用意し、周遊プランで「もう一泊」を設計します。
まとめ:インバウンド 経済効果は「分かる→整える→分散する」でまだまだ伸びていく見込み
まず、最新データが示すとおり人数と消費は過去最高圏です。さらに、多言語・キャッシュレス・予約DXの4点セットを先に整えると、宿泊・買物・飲食という中核費目の摩擦が下がります。つまり、インバウンド 経済効果は「量(来訪者)×質(単価/滞在)×分散(地方/季節)」の掛け算で決まり、したがって地方誘客とオフピーク設計が次の成長戦略です。
結果として、地域に残る付加価値と雇用が増え、日本全体の観光立国が持続可能な形で進化しいくことでしょう。