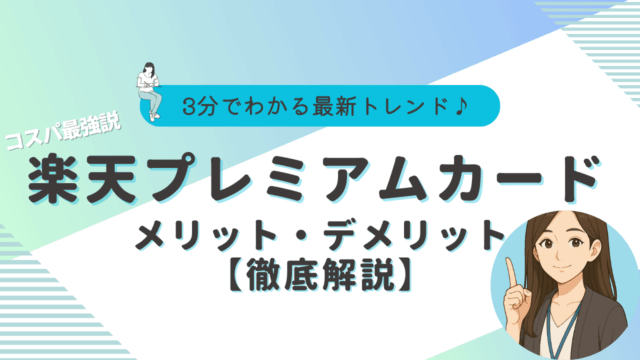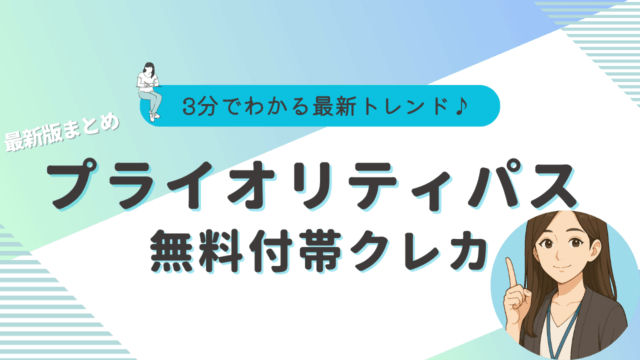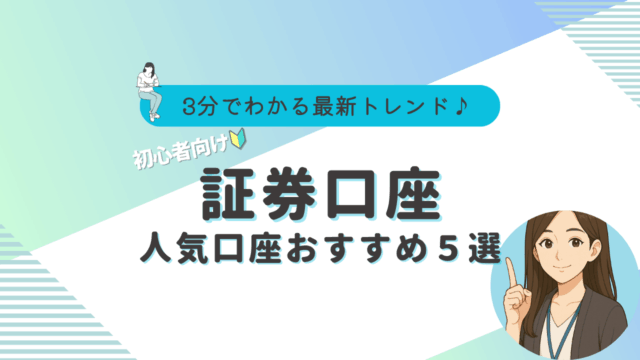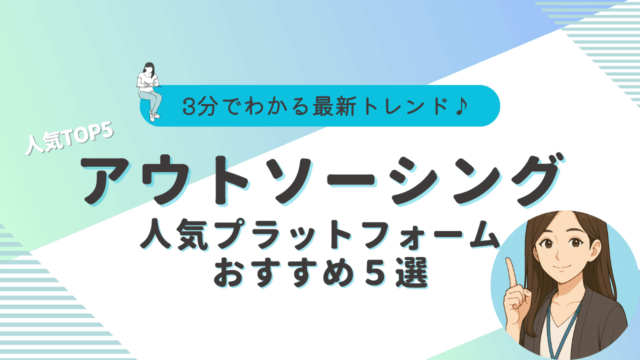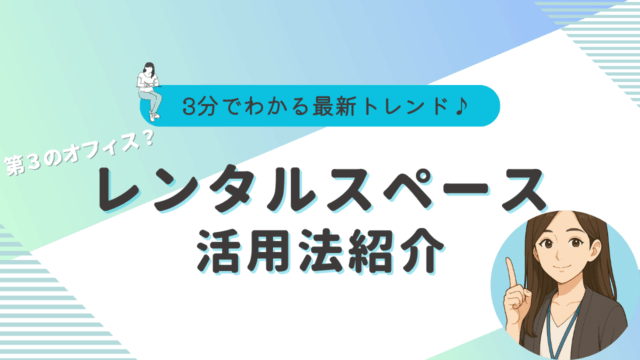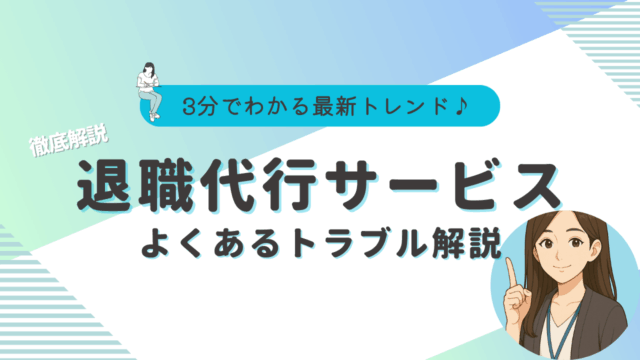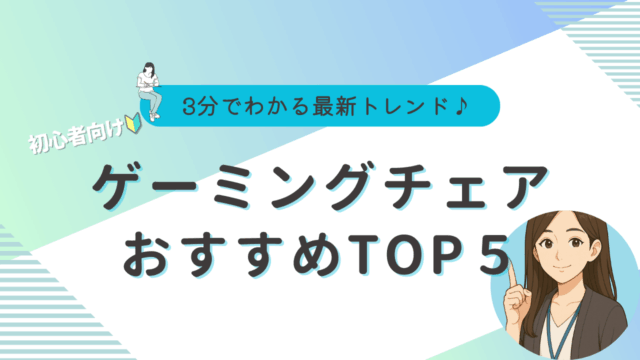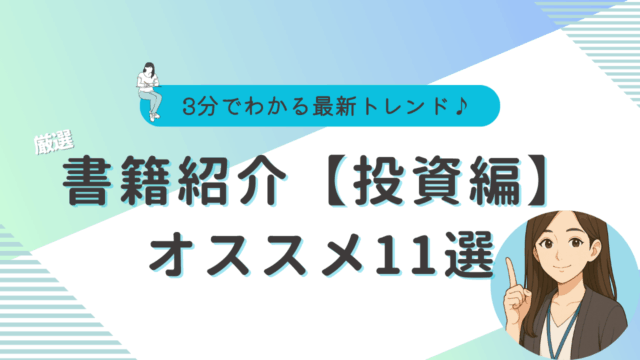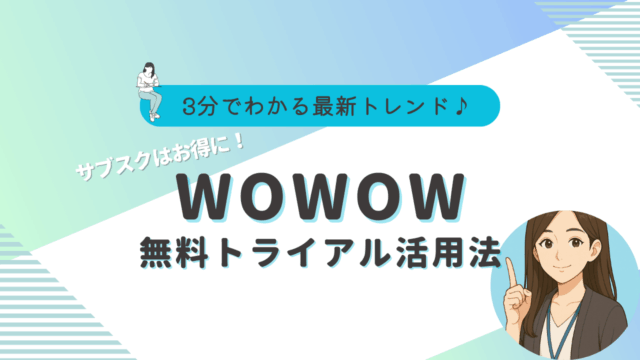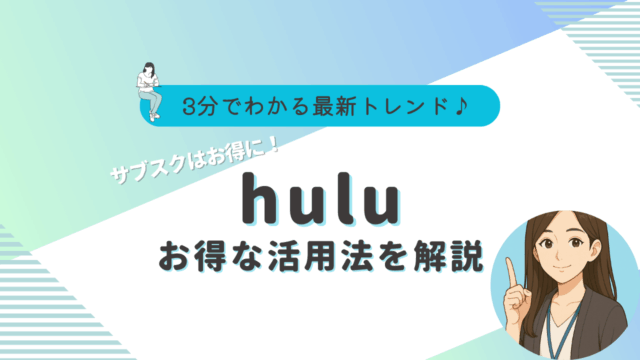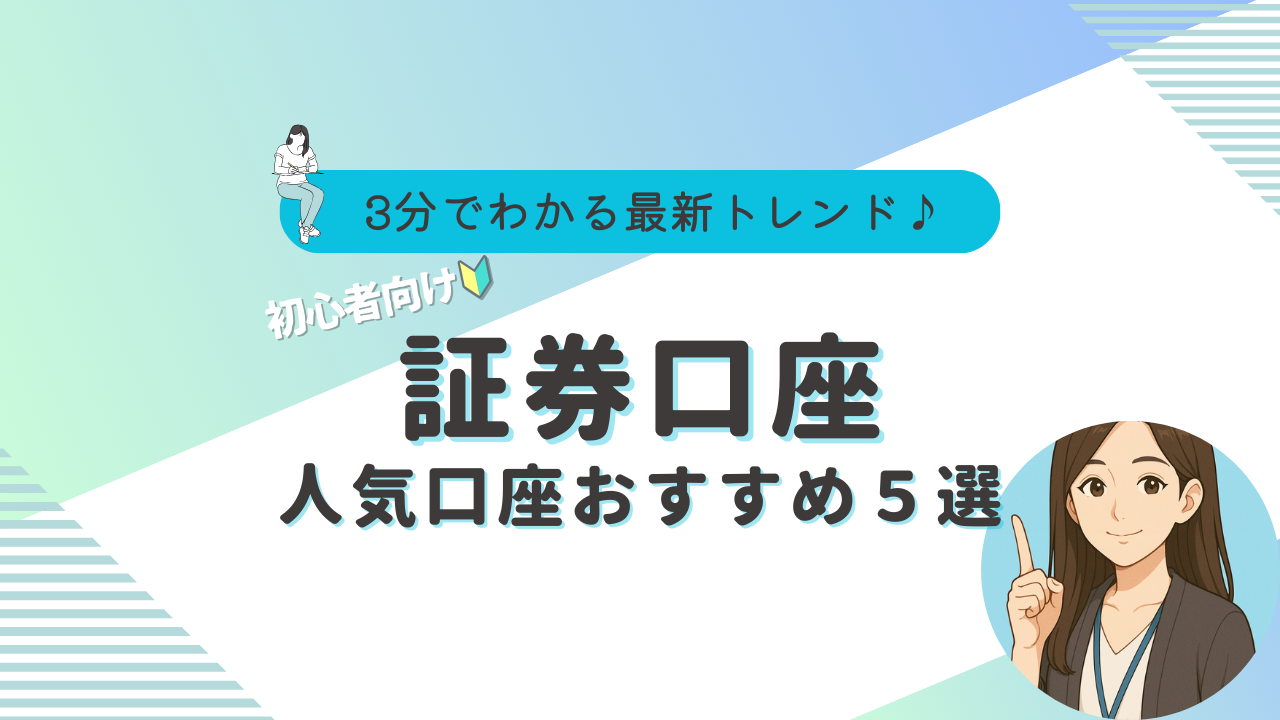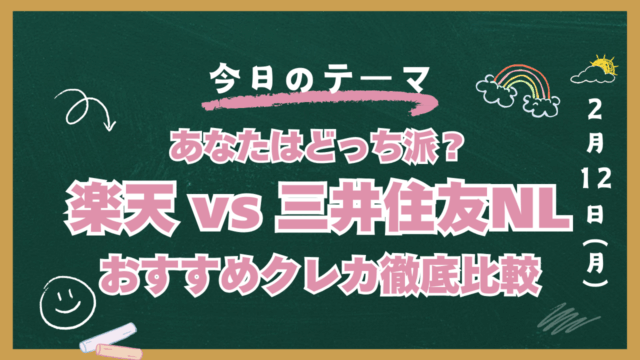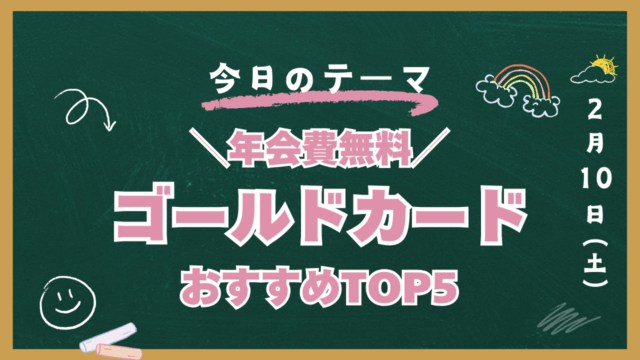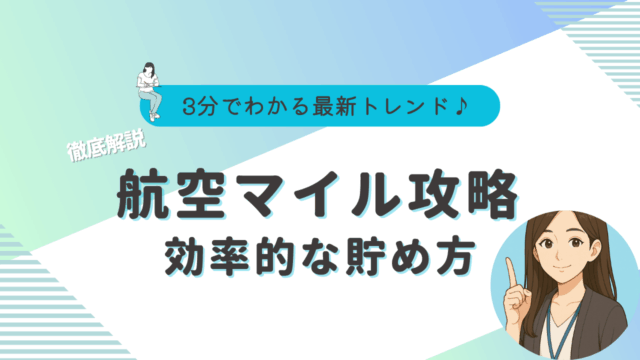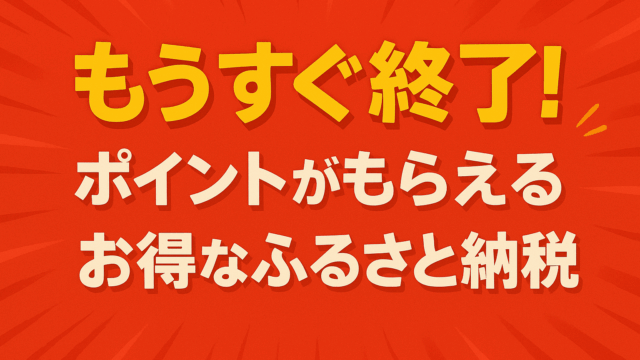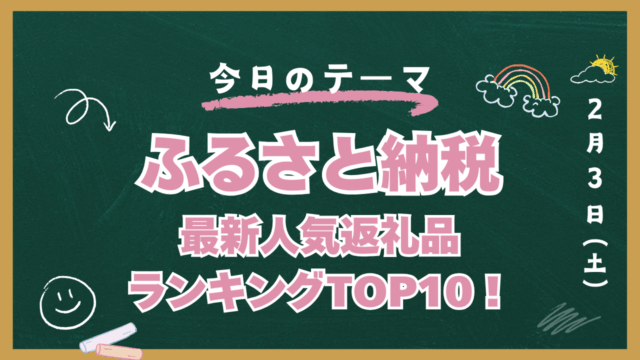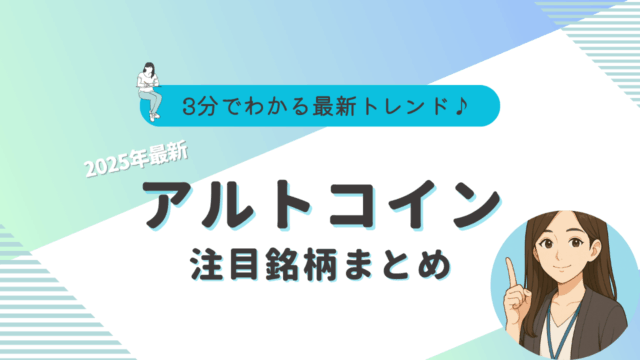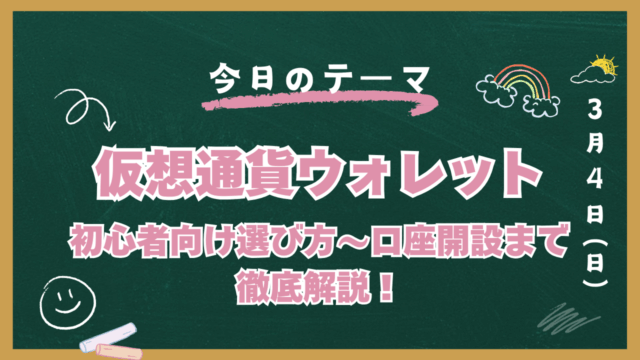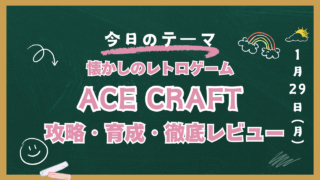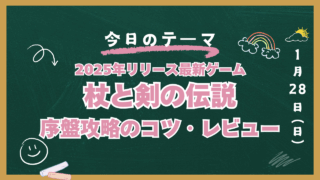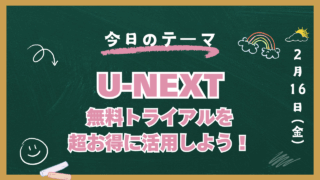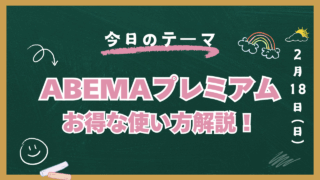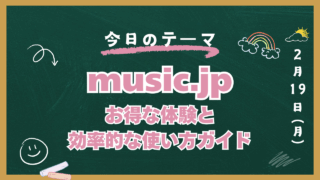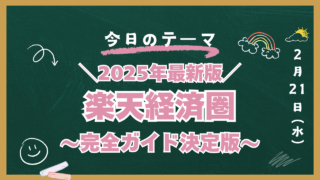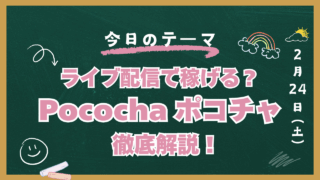もくじ
証券口座 おすすめ 初心者|2025年の全体像
証券口座 おすすめ 初心者が迷わず始めるなら、SBI証券/楽天証券/PayPay証券/マネックス証券/DMM株(DMM.com証券)の5口座から選べば失敗はしにくいです。さらに、新NISAの恒久化で非課税投資の土台が整い、クレカ積立やポイント投資の拡充で「少額×自動×継続」が当たり前になりました。そのため、まずは手数料・最小投資額・ポイント還元・アプリの使いやすさを軸に、自分の投資スタイルへ最短距離で合う1口座を決め、次に目的別に2〜3口座を使い分けるのが実務的です。
なお、新NISAでは生涯非課税保有限度額1,800万円かつ枠の再利用が可能になり、長期積立との相性が一気に高まりました。
ちなみに本記事では詳しく取り上げませんが、LINE証券は2024年8月にサービス終了・資産は野村證券へ移管されています。
証券口座 おすすめ 初心者向けの選び方(最短チェックリスト)
選定基準は次の5つさえ押さえれば十分です。さらに、初心者の詰まりどころも一緒に潰しておきます。
| 選定基準 | 詳細 | 初心者の要点 |
|---|---|---|
| 手数料/コスト | 国内株・米国株・投信・為替手数料 | NISAで無料化の範囲と単元未満株のコストを確認 |
| 最小投資額 | 100円積立/1,000円から株など | **「少額で慣れる」**導線があるか |
| アプリUI/速度 | 直感操作・約定/入金の速さ | 迷わず買える・クイック入金の有無 |
| ポイント/クレカ積立 | 還元率・対象ファンド | 毎月の自動化×還元で続けやすい |
| 取扱の広さ | 米国株/ETF/投信/オルタ | 将来やりたい投資まで見据える |
ポイント投資の制度・カード選びは ポイント投資用クレカ、楽天経済圏の設計は 楽天経済圏ガイド、完全放置型なら ロボアドバイザー特集 が補助になります。
証券口座 おすすめ 初心者向け TOP5【2025年版】
さて、どの口座にも一長一短はあります。そのため、向き不向きを明確化し、役割で選ぶのが正解です。
1位:SBI証券(総合力×口座数No.1)

理由:NISA・米国株・S株(単元未満株)・投信の総合力が最強クラス。さらに、2025年3月に1,400万口座を突破し、国内ネット証券の中核的存在です。そのため、最初の1口座として最有力。
補足:NISAの米国株手数料など**「ゼロ革命」や、SBI厳選の米国ETF買付手数料無料**の枠も要チェック。
👉 【SBI証券公式】
2位:楽天証券(ポイント投資×クレカ積立の王道)

理由:100円からの投信積立とクレカ積立(最大2%対象銘柄あり)で「自動×還元」が回しやすい。さらに、NISAの国内株手数料0円やポイント利用の導線が充実。そのため、給与日連動の毎月定額積立で投資習慣を固めたい人に最適。
👉 【楽天証券公式】
3位:PayPay証券(超少額×直感)

理由:アプリ3タップで少額売買、1,000円から日米株・投信が買える設計。さらに、PayPay資産運用なら100円以上1円単位からの米国株投資も可能。つまり、とにかくハードルを下げたい層に刺さります。
👉 【PayPay証券公式】
4位:マネックス証券(米国株ツールが強い)
理由:米TradeStation社由来の米国株アプリが高機能。チャート発注・レーダースクリーンなど中級者以降まで不満が出にくい。一方で、最初は機能が多いぶん、慣れの時間を見込める人向き。
👉 【マネックス証券公式】
5位:DMM株(かんたんモード⇄ノーマル切替)

理由:「かんたんモード」で超シンプル操作、さらにワンタップのクイック入金やノーマルモードへの切替で板・指標発注にも伸ばせる二刀流。つまり、アプリ体験で選びたい人にハマる。
👉 【DMM.com証券公式![]() 】
】
証券口座 おすすめ 初心者|主要5社「超」比較表(ざっくり版)
| 口座 | 最小投資 | 強み | 弱み/注意 | こんな人に |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 投信100円/S株可 | 総合力・NISA・米国株 | 機能が多く迷うことも | 王道の最初の1口座 |
| 楽天証券 | 投信100円 | ポイント/クレカ積立 | 銘柄次第で還元率差 | 自動積立×還元 |
| PayPay証券 | 1,000円〜(資産運用は100円〜) | 直感UI・少額 | 本格分析は物足りる場面 | まず触る→慣れる |
| マネックス | 通常単元/投信100円 | 米国株アプリ強 | 操作慣れが必要 | 米株を伸ばす |
| DMM株 | 通常単元 | かんたん⇄ノーマル | 情報ツールは別途検討 | スマホ完結派 |
手数料の無料化トレンド(現物/信用/単元未満株の無料化など)はSBI・楽天が先導し、総合コストでの差は小さくなりつつあります。しかし、個別のキャンペーンやNISA適用範囲は必ず最新ページで再確認してください。ダイヤモンド・オンライン
証券口座 おすすめ 初心者|タイプ別マッチング表
自分の状況に次のどれかが当てはまれば、そのまま決めて良いです。
| タイプ | すぐの最適解 | 次の一手 |
|---|---|---|
| 給与日ごとに自動で積立したい | 楽天証券(クレカ積立) | SBI証券も追加、投信を役割分担 |
| 米国株に本腰 | SBI証券 or マネックス | ETFはSBI無料枠も確認 |
| まずは100円〜1,000円で練習 | PayPay証券(資産運用100円〜/アプリ1,000円〜) | 慣れたらSBI/楽天で積立拡張 |
| UI最優先で迷いたくない | DMM株(かんたんモード) | ノーマルへ切替で板・指標へ |
| 投資はなるべく自動化 | 楽天×SBIで積立/NISA分散 | ロボアドも視野→ロボアド特集 |
証券口座 開設 初心者向け手順書
次の7ステップに沿えば今日から着手→来月には自動化まで行けます。
-
目的を決める:長期積立か米国株か。さらに、毎月の投資上限(例:手取りの5〜10%)を先に固定。
-
1口座を決める:上のマッチング表で最短合致を選択。そのため、迷いを減らす。
-
口座開設:アプリで本人確認(マイナンバーカード等)→最短翌営業日で可。
-
入金ルール:給料翌営業日に自動入金orクイック入金。さらに、楽天/SBIは入金導線が強い。
-
積立を設定:投信は毎月/毎週、クレカ積立で還元×自動。例えば、楽天はファンド条件次第で最大2%対象。楽天証券
-
NISAの使い分け:積立は投信中心、成長枠は米国株/ETFなど役割分担。そして、売却分の枠再利用を理解。
-
2口座目で拡張:米国株ツール=マネックス、少額練習=PayPayなどで最適化。
体験談:副業ブロガーが「3口座併用」で変わったこと
まず、私は2023年に楽天証券で投信積立を開始。しかし、米国株の個別株に興味が出てSBI証券を追加。さらに、家族に投資を教えるためPayPay証券で1,000円の練習枠を作りました。その結果、
-
毎月定額の自動化で「忘れても続く」設計になり、
-
米株はSBIの無料枠/機能で満足度が上がり、
-
家族の練習はPayPayの直感UIで心理ハードルが下がる、
という形に落ち着きました。一方で、口座分散でのログイン管理が面倒になる瞬間も。だから、パスワード管理と月次ルーティン表(積立日・NISA配分・入金日)を作って**運用を“家事化”**しています。
証券口座 おすすめ 初心者|よくある誤解と回避策
さて、初心者が陥りやすい落とし穴を先回りで潰しておきましょう。
-
「無料なら何でもOK」:為替手数料・スプレッド・銘柄毎条件など見えにくいコストが残ります。そのため、NISAの無料範囲と通常取引の手数料を別々に確認。
-
「1社で全部」:一方で、アプリは相性です。つまり、積立口座+米国株口座で役割分担した方が迷いが減る。
-
「LINE証券が初心者向き」:しかし、すでにサービス終了。つまり、最新状況へアップデート必須。
証券口座 おすすめ 初心者|拡張の道(ポイント投資・ロボ・仮想通貨)
例えば、現金フローの効率化ならポイント投資が有効です。さらに、カード選びは高還元率クレカとポイント投資クレカ比較を。
一方で、完全放置で積立したいならロボアド投資へ。そして、リスク分散の視点で暗号資産まで学ぶなら仮想通貨 取引所おすすめも参考に。
基礎の見取り図(はじめての設計)
| 項目 | まず決める | つまずきやすい点 | 対処 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 長期積立 / 米株 / 少額練習 | 優先順位が曖昧 | 1つに絞る→次を足す |
| 入金 | 給与日翌営業日 | 忘れる | 自動入金/クレカ積立 |
| NISA | 積立/成長の配分 | 枠の再利用を誤解 | FSAの図解で確認 |
| 継続 | ルーティン化 | 変動で感情的 | 定額×分散×放置 |
口座×用途マッピング(実務ショートカット)
| 用途 | 最短の選択 | 補足 |
|---|---|---|
| 投信の自動積立 | 楽天(クレカ最大2%対象銘柄あり) | 銘柄要件あり 楽天証券 |
| 米国株を育てる | SBI or マネックス | 米ETF無料枠/SBI、ツール/マネックス SBI SecuritiesMonex Securities |
| 少額で練習 | PayPay(100円〜/資産運用) | アプリは1,000円〜 PayPay Securities+1 |
失敗回避チェック(出発前の最終点検)
-
さらに:毎月いくらまで投資?(可処分の5〜10%)
-
しかし:一括投資はしない(時間分散を最優先)
-
つまり:NISA枠は長期の核、課税枠は試行・短期
-
例えば:投信=積立、米株=ETF/高配当、個別は少額で
よくある質問(FAQ)

Q1. 証券口座 おすすめ 初心者は「1社」で十分ですか?
A. まずは1社でOKです。しかし、投信の自動化と米国株の2軸を回す段階で2〜3社に分けると、つまり「やりたいことが最短でできる」体制になります。
Q2. NISAは何から始めれば?
A. つみたて投信を核にして、その上で成長枠に米国株/ETFを。さらに、売却後の枠再利用の仕組みを理解しておくと設計が楽です。
Q3. クレカ積立の還元はどれくらい?
A. 楽天証券では対象ファンド・カード種別に応じ最大2%の還元枠があります。一方で、銘柄要件があるため対象一覧の最新情報を必ず確認しましょう。
Q4. 100円や1,000円の少額からでも意味はありますか?
A. **あります。**まず変動に慣れること、さらに自動化のルーティンを作ることが本質です。例えば、PayPay資産運用の100円〜や、投信の100円積立が練習に最適です。
Q5. よく見かける「LINE証券」はどうなった?
A. サービス終了(2024年8月)で、資産は野村證券に移管されています。そのため、LINE証券前提の解説は現状に合いません。
まとめ|証券口座 おすすめ 初心者の最短戦略
結論:証券口座 おすすめ 初心者が2025年に最短で成果へ向かうには、
-
目的を1つに絞って最初の1口座(SBI/楽天/PayPay/マネックス/DMM)を開く、
-
クレカ積立×NISAで自動化、
-
米国株はSBIかマネックスで拡張、
-
少額練習はPayPayで感情コントロール、
という流れが堅実です。そして、情報は必ず公式の最新ページで裏取りし、運用は**「定額×分散×長期」を崩さないこと。これらをうまく実践できれば、株式投資があなたの収入のひとつになる日も近いはずです。